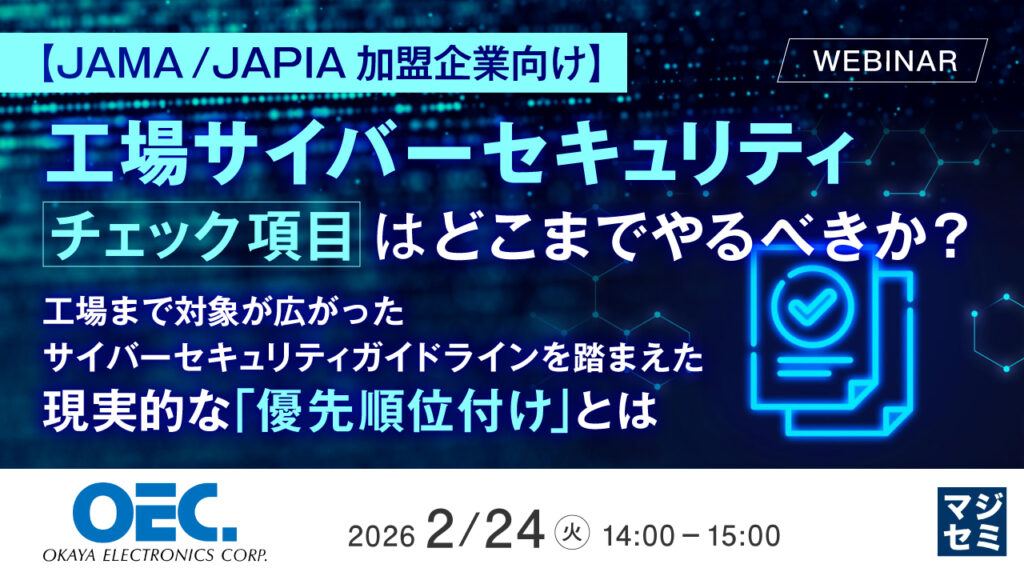半導体業界は、経済安全保障の観点からも重要な産業であり、サイバー攻撃の標的となっています。
本記事では、半導体業界におけるサイバー攻撃の現状、具体的な対策方法、導入事例、関連ガイドラインなどを解説します。
半導体業界におけるセキュリティの重要性
半導体業界におけるセキュリティは、企業の競争力と国の経済安全保障を支える重要な要素です。なぜなら、半導体は自動車、通信機器、医療機器、防衛機器など、あらゆる産業の根幹を担う戦略物資であり、あらゆる産業の根幹を担う戦略物資であり、その設計技術や製造プロセスが外部に漏洩すれば、企業の存続はもちろん、国家レベルでの安全保障にも重大な影響を与えるためです。
近年、国家間の地政学的対立の影響で産業スパイの動きが活発化し、さらにサプライチェーンのグローバル化によりセキュリティリスクが拡大しています。また、知的財産の流出は企業価値を大きく損なう要因にもなります。
セキュリティ対策は単なるコストではなく、企業の持続的成長と国家の競争力を守るための必須要件だといえるでしょう。
経済安全保障と半導体
半導体は現代のあらゆる電子機器に不可欠な存在であり、経済安全保障の観点からも極めて重要な資源です。半導体の供給が滞ると、軍事、通信、自動車など主要産業が大きな影響を受けるため、安定供給の確保は国家戦略の根幹をなします。
主要技術の流出は国家競争力の低下につながり、特定国への過度な依存は地政学的なリスクを高めます。実際、2021年の世界的な半導体不足は、各国の産業政策や外交戦略にも波及しました。日本政府もこの事態を受けて、経済産業省が策定した「半導体・デジタル産業戦略」(2021年6月)※1では、経済安全保障上の観点から半導体サプライチェーンの強靭化と情報セキュリティ強化が明確に掲げられています。
企業にとって半導体のセキュリティ対策は、自社の安定経営だけでなく、国家レベルの経済安全保障にも寄与する取り組みといえます。
知的財産の保護
半導体業界では、設計技術や製造プロセスなどの知的財産が企業の競争力を支える基盤となっています。知的財産は膨大な研究開発投資によって生み出されるものであり、その保護は事業継続に直結する課題です。
万が一知的財産が流出した場合、競合他社に技術的な優位性を奪われるだけでなく、模倣品によってブランド価値が損なわれる恐れもあります。
被害を未然に防ぐには、アクセス制御や監視体制の強化に加え、従業員教育を徹底することが不可欠です。知的財産の保護は、競争力の源泉を守るための重要なセキュリティ施策です。
サプライチェーンセキュリティ
半導体業界のサプライチェーンは、業界固有のニーズをサポートするために高度に専門化されています。この専門化を業界のバリューチェーンに落とし込むと「上流」「中流」「下流」に分けられます。
上流:集積回路(IC)の設計やレイアウト
中流:IC製造(ウエハー製造および処理とも呼ばれ、最も資本と技術が集中する)
下流:集積回路(IC)のパッケージングと性能テスト
最終的に製品を完成させるには、PCBモジュールや基板アセンブリなどの周辺産業が必要です。
具体的には、
IC設計会社:Qualcomm、Broadcom、MediaTek
ウエハー製造および組立ベンダー:SMC、Samsung、GlobalFoundries、ASE、Amko
などが、代表的な企業として挙げられます。
![]()
半導体業界におけるサプライチェーンセキュリティは、製品の品質と信頼性を守るために欠かせません。なぜなら、サプライヤーを介した不正アクセスやマルウェアの混入は、企業の製品やブランドに深刻な影響を及ぼすためです。
例えば、外部委託先のソフトウェアにマルウェアが仕込まれている場合、製造ライン全体の操業停止を余儀なくされるケースもあります。
サプライチェーン全体にわたるセキュリティ対策は、今後の半導体業界において業界標準となるべき重要な取り組みだといえるでしょう。
半導体業界を狙うサイバー攻撃の手口
半導体業界は高度な技術力と国際的な影響力を持つため、サイバー攻撃の主要な標的となっています。特に、機密情報や製造データを狙う攻撃が増加しており、セキュリティ脅威への対応が急務です。
攻撃手法には多様な種類がありますが、共通して狙われるのは「情報資産」と「供給網の脆弱性」です。半導体関連企業では、設計ファイルや製造工程に関する情報が漏えいすることで、経済的損失や信頼低下といった深刻な影響が生じます。
このような背景から、業界全体でのリスク共有と対策の標準化が求められています。サイバー攻撃に対する備えは、競争力維持のための必須条件です。
1.未承認EDAツールとリモート接続による脆弱性リスク
中小のIC設計企業では、EDAツールの高コストにより、1台のサーバーにソフトウェアを集中管理することが一般的です。しかし、アクセス権のないインターンやエンジニアが個人のPCに正体不明のEDAツールをインストールすることで、ネットワークにセキュリティリスクを持ち込む可能性があります。
2020年以降の在宅勤務拡大に伴い、VPNなどのリモート接続経由で攻撃者に新たな侵入口を提供する事例も増加。たとえば、EDAベンダーのケイデンス社も2021年にLog4jの脆弱性の影響を受けました。こうした背景から、隔離が難しい環境では脆弱性管理が不可欠です。
また、中小企業は高額な機器の調達が困難なため、半導体のパッケージングやテストをOSAT工場に委託することが一般的です。OSAT側のレガシー機器や共有テストソフトウェアの使用により、1つの脆弱性が生産ライン全体に波及するリスクが高まっています。
2. 製造装置のメンテナンスのための危険なリモート接続を狙った攻撃
半導体製造に使用される装置は、フロントエンド・バックエンド問わず精密に設計されており、ユーザー側で自由にプログラムを変更することはできません。そのため、機器に直接セキュリティ対策を導入することが難しく、一般的なIT向けソリューションはOT環境に適用しにくいのが現状です。
装置の修理や障害対応にはメーカー支援が不可欠であり、一部ではリモート接続による保守サービスが提供されています。しかし、攻撃者がこの接続用トークンを入手すれば、生産ライン全体が危険にさらされる可能性があります。
実際、ASMLは過去にデータ窃取などのサイバー被害を公表しており、先端技術を持つ企業は国家支援の攻撃グループの標的となりやすい状況にあります。※3
3. 脆弱性管理プラットフォーム不足を狙ったマルウェア攻撃
ランサムウェアは、システム内のファイルを暗号化し、復号の代わりに金銭を要求するサイバー攻撃です。半導体業界では、製造ラインの停止や研究データの喪失といった甚大な被害が発生する可能性があります。
例えば、300mmウエハーの製造には、8,000~15,000のエンドポイントデバイスを含む約250~300の重要な資産があります。(※2)このような大規模でパッチが適用されていない環境は、簡単にマルウェアの温床になる可能性があります。
攻撃者は業界の社会的影響力の大きさを逆手に取り、復旧のために多額の身代金を請求します。生産拠点が数日間にわたり停止すると、数十億円規模の損失が発生する可能性もあるでしょう。
こういった場合、製造現場では、初期段階でそれを検出し、多数のデバイスを管理するための一元化された視覚的な管理プラットフォームを必要となります。
さらに、多くの重要な資産は高度すぎるため、各エンジニアは資産の実際のソフトウェア構成を理解できません。したがって、ネットワークおよびシステムログイベントの記録を除き、資産所有者が新たに発見された脆弱性に迅速に対応し、それに応じて組織の軽減計画を実行できるように、資産のソフトウェア部品表(SBOM)も理解する必要があります。
4. 内部関係者の関与によるAPT(高度持続的脅威)攻撃
半導体産業は1980年代からグローバル化が進み、組立や最終テスト工程は労働集約型であることから、多くの欧米企業が早期に東南アジアや東欧に製造拠点を設立しました。これは、低コストの人材確保や現地政府の優遇策を活用するためです。(※4)
グローバル規模での業務拡大に伴い、従業員や委託先による機密情報の管理はより複雑になります。このような環境では、内部関係者が意図的または不注意に機器を操作することで、APT(Advanced Persistent Threat)攻撃の足掛かりとなるリスクが高まります。特に、内部からの協力を得た攻撃は長期間発覚しにくく、重要データや製造プロセスが漏洩するおそれがあります。
半導体業界特有のサプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃とは、企業自身ではなく、その取引先やサードパーティベンダーを経由して侵入するサイバー攻撃の手法です。特に半導体業界では、設計、装置、材料、製造、後工程(OSAT)など多層的かつ国際的なサプライチェーンで構成されており、攻撃対象が広範囲に及ぶため、リスクが極めて高い業種とされています。
攻撃者は、セキュリティ対策が不十分な装置メーカーやEDAツール開発元、あるいは後工程を担う委託先などを突破口に、最終的に設計元やファブ企業の中核システムに侵入します。
こうした背景を踏まえ、半導体製造装置とそのソフトウェアのサイバーセキュリティ要件を定義したSEMI E187(サイバーセキュリティ対応製品の提供要件)およびSEMI E188(製造装置に対するセキュリティ検証のガイドライン)は、産業界全体で重要性を増しています。これらのガイドラインは、装置ベンダーとファブの双方に求められるセキュリティ要件や検証方法を標準化するものであり、サプライチェーン全体のセキュリティ確保において実効性のある基準です。
E187とE188、2つの規格の違いとは
サプライチェーン全体を守るための、相互関係と境界線を整理
半導体業界におけるセキュリティ対策
半導体業界では、セキュリティ脅威の高度化に対応するため、総合的な対策の導入が不可欠です。なぜなら、サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、従来の境界防御だけでは機密情報や製造プロセスを守りきれないためです。
たとえば、ゼロトラストや多要素認証、エンドポイント保護といった多層的な対策を組み合わせることで、リスクの低減が可能になります。さらに、SIEM(セキュリティ情報イベント管理)を活用してインシデントを早期に検知・対応する体制を整えることも求められます。
セキュリティガイドラインの策定と継続的な改善を通じて技術的な防御と人的な教育の両面から対策を強化することが、企業全体の安全性を高める鍵となります。
ゼロトラストセキュリティ
ゼロトラストセキュリティとは、「何も信頼しない」ことを前提にすべてのアクセスを検証するセキュリティモデルです。従来の境界型セキュリティと異なりネットワーク内の通信に対しても常に検証を行うため、内部不正や侵入後の被害拡大を抑える効果があります。
半導体業界では次の3つのゼロトラストセキュリティが考えられます。
- インバウンドデバイスのゼロトラスト
このサイバーセキュリティポリシーは、デバイスが敷地内に到着した瞬間から適用されます。オンボーディング準備中の新規デバイスであっても、サプライチェーン攻撃のリスクを軽減するために、事前のスキャンが必要です。
実際に、サイバー攻撃者が出荷前の段階でデバイスを侵害し、サイバーインシデントを引き起こした事例も報告されています。 - アプライアンスのゼロトラスト
従来のウイルス対策ソフトウェアは資産に行き詰まり、クラッシュや遅延を引き起こす可能性があります。これに対応するにはエンドポイントセキュリティが必要です。PCやモバイル端末など個別の機器に対して保護機能を設けるセキュリティ対策であり、リモートワークやBYOD(私物端末の業務利用)の普及に伴い、半導体業界でも重要性が増しています。エンドポイントが攻撃の入り口となるケースが多いため、ウイルス対策ソフトやEDR(Endpoint Detection and Response)の導入が推奨されます。これにより、異常な挙動を早期に検知し、感染拡大を防ぐことが可能です。
- ネットワークのゼロトラスト
ネットワーク内の不要な「ドア(通信経路)」が、ファイアウォールやIPSアプライアンスによって設定されたルールに基づき封鎖されていれば、攻撃者によるOTネットワークへの侵入ははるかに困難になります。
これらの通信ルールは、どの資産同士が業務上通信する必要があるかに基づいて厳密に設計され、ネットワークは管理・監視しやすいセグメントに分割されます。
また、レガシー資産やパッチが適用できない資産については、仮想パッチを適用することで脆弱性を保護し、攻撃者による悪用を防ぐことができます。
セキュリティ情報イベント管理 (SIEM)
SIEMは、ネットワーク上のログやアラート情報を集約・分析し、異常を早期に発見・対応するためのセキュリティシステムです。複数のセキュリティツールを横断的に連携させることで、全体的な可視性を高められます。
たとえばSIEMを導入すると、従来気づけなかった不審な通信を早期に検知し、インシデント発生前に遮断できます。
半導体業界のような複雑なシステム環境では、SIEMによる監視とインシデント対応の自動化が、セキュリティ対策の中核となるでしょう。
脆弱性管理
脆弱性管理は、ソフトウェアやシステムに存在するセキュリティホールを特定・修正し、攻撃のリスクを低減するためのプロセスです。新たな脆弱性は日々発見されており、継続的なスキャンとパッチ適用が求められます。
半導体製造ラインにおける制御システムや、生産管理ソフトなどにも脆弱性は存在します。脆弱性を放置すれば、攻撃者にとって格好の標的となってしまうでしょう。
計画的かつ継続的な脆弱性管理は、日常業務への影響を最小限に抑えながら、システムの安全性を保つために欠かせない取り組みです。
半導体業界のセキュリティ対策事例
台湾の半導体製造企業TSMCでは、2018年にランサムウェア「WannaCry」の亜種に感染し、製造ラインの操業が約3日間停止。最大で約190億円の損失が発生しました。このインシデントは、感染した製造用機器がウイルスチェックを経ずにネットワークへ接続されたことが発端でした。内部ネットワーク内で感染が連鎖的に拡大し、複数の制御用コンピュータが暗号化されて機能を停止しました。
この事例を受け、ウイルスチェックの徹底やネットワークのセグメンテーション、不要な通信ポートの遮断、定期的なパッチ適用などが有効な対策として整理されています。特に、サプライヤーや外部関係者が持ち込む機器への対策、物理的な入退管理、バックアップ体制の強化が重要です。このような対策を通じて、人的ミスやサプライチェーンを起点とするリスクを低減できます。
半導体業界関連ガイドラインと規格
半導体業界では、国際的に認知されたセキュリティガイドラインや規格に準拠することが、顧客や取引先からの信頼を獲得する上で重要です。なぜなら、半導体産業チェーン内の企業は高度に連携しており、サプライチェーンのセキュリティはすでに半導体業界が十分に理解し、対応しなければならない問題となっているからです。
その中で半導体業界向けのガイドラインを紹介します。
SEMI E 187 / E188
SEMI E187/E188とは、半導体製造装置におけるセキュリティリスクへの対策を体系的にまとめた規格で、世界的な半導体業界団体であるSEMIが、2022年に発表しました。両規格は、互いに補完し合い、連携してサイバー脅威から半導体製造装置を保護します。多くの半導体サプライチェーンは両規格の関係性を理解しておくことが今後より求められることが考えられます。
SEMI E187
SEMI E187はあたらしい装置の開発段階に焦点を当てており、オペレーティングシステムのセキュリティ、ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、セキュリティ監視の4つの基本要素をカバーしています。特にWindowsおよびLinuxオペレーティングシステムを実行しているデバイスの場合、装置サプライヤーは装置の発送前にこれらのセキュリティ機能を実装することが義務付けられています。SEMI E187は、これらの装置におけるサイバーセキュリティ機能を標準化することにより、生産ラインに導入される新しい装置のための安全な基盤を築きます。
半導体装置の「設計・開発」に必要なセキュリティ要件とは
実装すべき技術仕様を網羅したリファレンスガイド
SEMI E188
SEMI E188はSEMI E187とは対照的に、新装置だけでなく既存の装置や、コンピュータ、コントローラ、PLCなどのすべてのコンピューティングデバイスにも適用できます。SEMI E188は、装置のマルウェアフリーの展開プロセスを強調しており、サプライヤーに対し、装置の配送、設置、メンテナンス中にマルウェアフリーの手順を厳守し、工場に入る前と後の両方で装置のセキュリティを確保することを求めています。
工場への「搬入・統合」を安全に行う
マルウェアフリーな納品を実現するコンプライアンス手順書
NIST SP 800-171
NIST SP 800-171は、連邦政府と取引のある民間企業が、CUI(Controlled Unclassified Information:管理対象非機密情報)を保護するためのセキュリティ要件をまとめたガイドラインです。
このガイドラインは、アクセス制御、監査と説明責任、識別と認証、インシデント対応など14のカテゴリ、110項目の要件で構成されています。半導体業界においては、機密設計情報や製造工程に関するデータを取り扱う際の指針として活用されることが多く、グローバルな信頼性確保にも寄与します。
導入企業にとっては、国際的な信頼性の向上と取引拡大の可能性を得られる点がメリットだといえるでしょう。
NIST SP 800-53
NIST SP 800-53は、情報システムと組織のセキュリティおよびプライバシー管理のための包括的なセキュリティ対策フレームワークです。政府機関向けに策定されていますが、高度なセキュリティ管理を求める民間企業にも広く適用されています。
このフレームワークは、リスク管理を軸に約20の管理カテゴリと1000項目を超えるセキュリティ対策で構成されており、セキュリティ対策の網羅性と実効性を高めたい企業にとって強力な指針です。
半導体業界では、特に重要インフラや防衛関連との取引がある企業が採用しており、より高度なセキュリティ要求に応えるための基盤として機能しています。
まとめ
半導体業界におけるセキュリティは、企業の競争力を維持するだけでなく、国家の経済安全保障にも深く関わる重要な要素です。サイバー攻撃の手口は巧妙化しており、業界全体が常に最新の対策を講じる必要があります。
多層的なセキュリティ対策を実装することで、リスクを大幅に低減することが可能です。加えて、SEMI E187 / E188や、NISTガイドラインのような国際規格への準拠は、グローバル市場における信頼性の担保にもつながります。
今後も、先進事例や標準規格を参考にしながら、自社のセキュリティ体制を定期的に見直し、持続的に強化していくことが求められます。セキュリティは一過性の対策ではなく、企業活動の根幹を支える継続的な取り組みです。
マルウェアによる「操業停止」を未然に防ぐ
既存設備を活かしたまま、国内初のセキュリティ適合を成し遂げた実例
TXOneにまずお気軽にご相談ください。
半導体業界のサイバーセキュリティ課題は常に変化しています。TXOneはお客様のサイバーセキュリティに関する課題について最適なOTセキュリティソリューションが提供できるよう、いつでもお手伝いさせていただきます。お問い合わせ内容を確認後、担当者より迅速にご連絡致しますので、お気軽にお問合わせください。
おすすめ記事
なぜ半導体工場はSEMI E187とSEMI E188を組み合わせるべきなのか
世界的な半導体業界団体であるSEMIは、2022年に2つの将来を見据えたサイバーセキュリティ規格、SEMI E187とSEMI E188をリリースしました。どちらも、半導体工場の安全確保に関心のある組織向けの近代化ガイドラインの先駆けであり、近いうちに半導体サプライチェーン全体で導入されることが期待されます。
参考文献
- ※1 半導体・デジタル産業戦略(令和5年 6月経済産業省 商務情報政策局)
- ※2 Mark Lapedus.” 200mm Shortages May Persist For Years”, Semiconductor Engineering, Jan 20, 2022, Accessed May 30 2022
- ※3 ASML PRESS RELEASE, “ASML recently discovered IT systems security incident”, ASML, May 1 2015, Accessed May 30 2022
- ※4 Lars Mönch, Reha Uzsoy, John W. Fowler, “A survey of semiconductor supply chain models