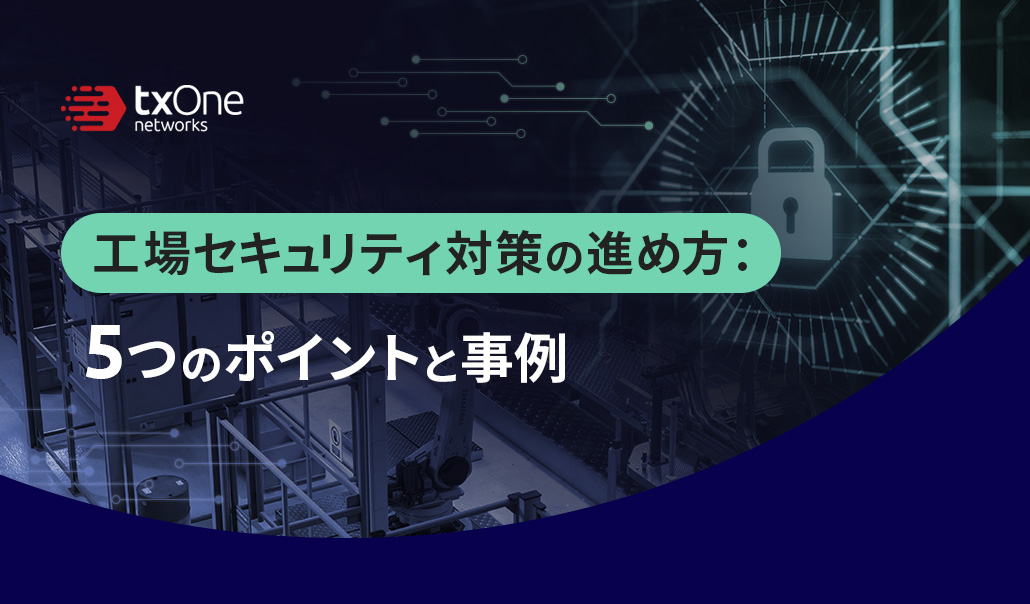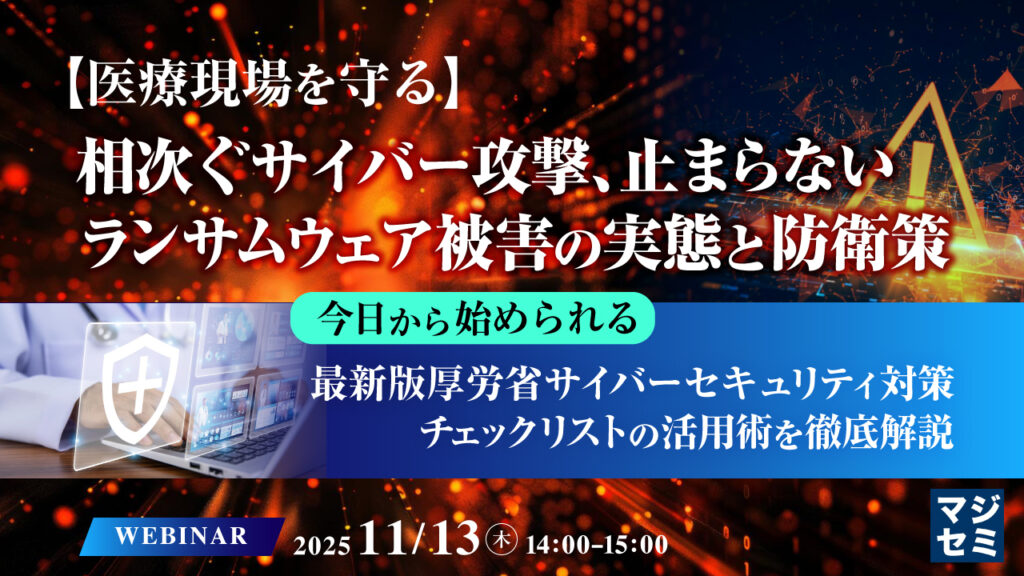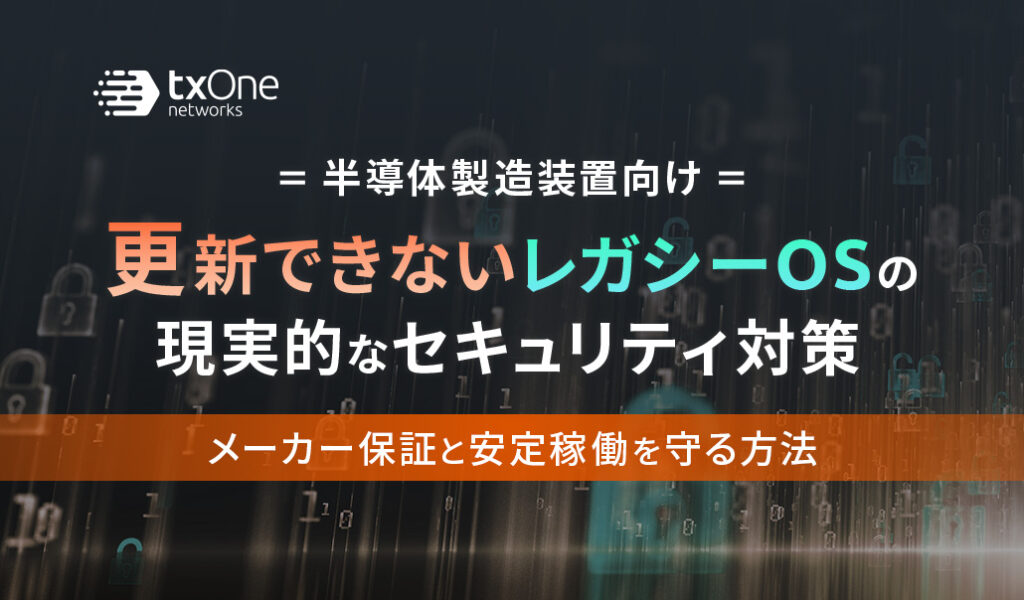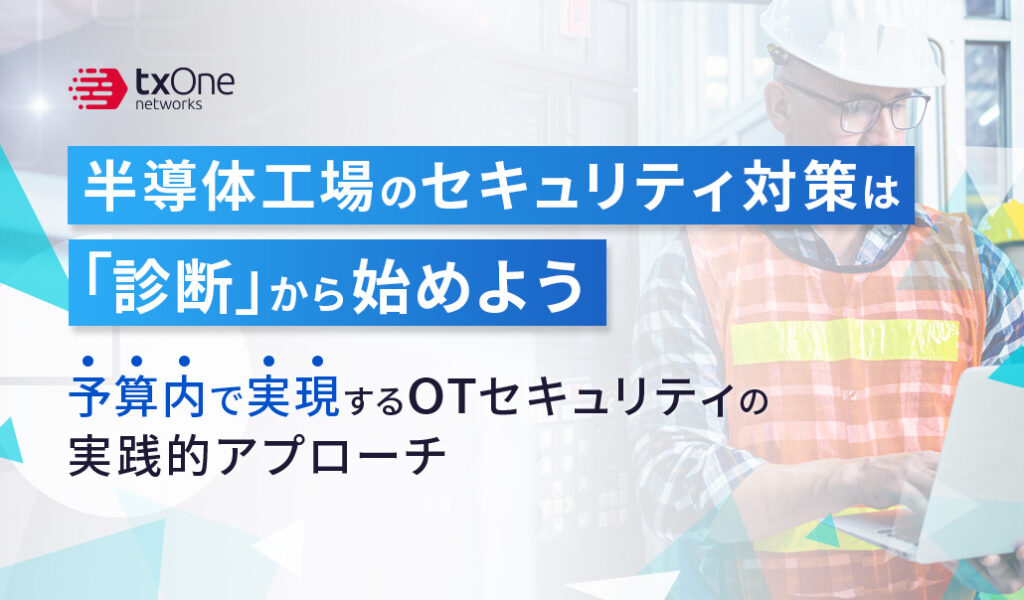工場のセキュリティ対策は、生産性や製品の品質維持に直結する重要な課題です。本記事では、工場におけるセキュリティリスク、効果的な対策の5つのポイント、導入事例、関連ガイドラインなどを解説します。
なぜ工場のサイバーセキュリティ対策が必要なのか?
工場のサイバーセキュリティ対策は、現代の製造業において欠かせない要素です。生産性や製品の品質を維持するためには、外部からの脅威に対する防御が不可欠です。
工場サイバーセキュリティとは、サイバー攻撃や不正侵入、情報漏えいなどのリスクから工場の設備・データ・人材を保護し、生産活動を安全に継続するための取り組みを指します。
ITとOTの統合やDX化が進む中で、工場はサイバー攻撃の標的となりやすくなっています。サイバー攻撃を受けると、企業の生産活動を妨げ重大な経済的損失をもたらす可能性もあるでしょう。そのため、工場のセキュリティ対策は、企業の競争力を維持するために必要不可欠です。
さらに、工場のセキュリティ対策は、企業の信頼性を高める要素でもあります。顧客や取引先は、情報が安全に管理されている企業を選びます。セキュリティ対策が不十分な場合、情報漏えいが発生し、企業の評判が損なわれるリスクがあります。
適切なセキュリティ対策を講じることにより、企業は信頼性を確保し長期的な成長を実現できるのです。
標的型攻撃の増加と製造業への影響
近年標的型攻撃が増加しており、製造業もその影響を受けています。標的型攻撃とは特定の企業や組織を狙ったサイバー攻撃の一種で、情報を盗み出すことを目的としています。製造業は、技術情報や顧客データなど攻撃者にとって価値のある情報を多く保有しているため、標的にされやすいのです。
攻撃が成功すると、企業は多大な損失を被ることになります。例えば、技術情報が流出すれば、競争優位性が失われる可能性があります。また、顧客データが漏えいすれば、信頼関係が損なわれ、取引先や顧客からの信頼を失う可能性もあるでしょう。
そのため、標的型攻撃に対する対策は製造業にとって非常に重要です。ネットワークの監視や不正アクセスの検知、従業員へのセキュリティ教育などが効果的な対策となります。

Volt Typhoon:忍び寄る脅威とサプライチェーンの盲点
本記事では、古いルーターやパッチ未適用のエッジデバイスを悪用するVolt Typhoonの手口と、見過ごされがちな信頼の裏に潜む危険について解説。運用環境の可視化やSBOM、セキュア・バイ・デザインといった対策の必要性も紹介します。
生産停止リスク
工場におけるサイバーセキュリティ対策が不十分な場合、サイバー攻撃や内部不正といったインシデント、あるいはシステム障害などの事故によって生産が停止するリスクが高まります。サイバー攻撃や内部不正によって生産設備やシステムが停止することは、製造業にとって致命的な問題です。生産が停止すると納期遅延や顧客への供給不足が発生し、企業の信用が損なわれる可能性があります。
生産停止のリスクを軽減するためには、システムの冗長化やバックアップ体制の整備が必要です。例えば、重要なデータやシステムを定期的にバックアップしておけば、万が一のインシデントや事故時にも迅速に復旧できます。
また、サイバー攻撃に対する防御策として、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入も効果的です。適切な対策を講じることにより、生産停止のリスクを最小限に抑え、安定した生産活動の維持が可能となります。
情報漏えいリスク
情報漏えいは、企業にとって深刻なリスクです。特に製造業では、技術情報や顧客データが外部に流出することは競争力の低下や信頼の喪失につながります。情報漏えいの原因は多岐にわたりますが、サイバー攻撃や内部不正が主な要因です。これらのリスクに対処するためには、包括的なセキュリティ対策が必要です。
対策としては、情報の暗号化やアクセス制御の強化が有効です。情報を暗号化することで、万が一データが流出しても内容が解読されるリスクを低減できます。また、アクセス制御を強化することで、情報への不正アクセスを防ぐことが可能です。
さらに、従業員に対するセキュリティ教育を実施し、情報管理の重要性を理解させることも重要欠かせません。こうした対策により情報漏えいのリスクを大幅に低減し、企業の信頼性を維持できます。
工場におけるセキュリティリスク
工場におけるセキュリティリスクは、生産性や製品の品質に直接影響を及ぼすため、無視できない重要な課題です。現代の工場は、デジタル化が進みさまざまなシステムやネットワークが導入されていますが、それに伴いセキュリティリスクも増加しています。
例えば、従業員のセキュリティ意識の低さや古いシステムの脆弱性、サプライチェーン攻撃といったリスクが考えられます。工場におけるセキュリティリスクを理解し適切な対策を講じることが、工場の安全性を確保し事業の継続性を維持するために不可欠です。
従業員のセキュリティ意識の低さ
従業員のセキュリティ意識の低さは、工場における大きなリスク要因となります。セキュリティに対する理解が不足していると、パスワードの使い回しや不適切なデータ管理など基本的なミスが発生しやすくなり、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まります。例えば、従業員がフィッシングメールに引っかかることで、重要な情報が外部に流出するケースも少なくありません。
リスクを軽減するためには、従業員への定期的なセキュリティ教育が不可欠です。例えば、セキュリティポリシーの理解を深めるための研修や、最新の脅威に関する情報提供を行うとよいでしょう。
さらに、セキュリティに関する具体的な行動指針を示し、従業員が日常的に意識できる環境を整えることも重要です。こうした取り組みにより、工場全体のセキュリティレベルを向上させることができます。
古いシステムの脆弱性
古いシステムの脆弱性は、工場のセキュリティにおける重大なリスクです。古いシステムは最新のセキュリティパッチが適用されていないことが多く、サイバー攻撃の標的になりやすいためです。特に、サポートが終了したシステムを使用し続けることは、攻撃者にとって格好の的となります。例えば、古いOSや未更新のソフトウェアが原因でマルウェア感染やデータの不正取得が発生する可能性があります。
リスクを軽減するためには、システムの定期的な更新と必要に応じた新しい技術の導入が必要です。最新のセキュリティパッチを適用し、サポートが終了したシステムは速やかに更新しましょう。また、システムの脆弱性を定期的にチェックし、問題が発見された場合には迅速に対処する体制を整えることも重要です。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、工場のセキュリティにおいて新たな脅威として注目されています。サプライチェーン攻撃とは、製品やサービスの供給過程において第三者が不正に介入し、システムやデータに悪影響を及ぼす攻撃手法です。
サプライヤーやパートナー企業のセキュリティが脆弱である場合、そこを経由して工場自体が攻撃されるリスクが高まります。例えば、サプライヤーのシステムがハッキングされ、そこから工場のネットワークにマルウェアが侵入するといったケースが考えられるでしょう。
攻撃リスクに対抗するためには、サプライチェーン全体のセキュリティを強化する必要があります。そのためには、サプライヤーやパートナー企業とセキュリティに関する情報を共有し、共同でセキュリティ対策を講じることが重要です。
また、サプライチェーン全体のセキュリティ状況を定期的に評価し、リスクが発見された場合には迅速に対応する体制を整えることも求められます。適切な対応を取ることにより、サプライチェーン全体の安全性を確保し、工場のセキュリティリスクを最小限に抑えることが可能です。
工場セキュリティ対策の5つのポイント
工場のセキュリティ対策は、生産性や製品の品質維持に直結する重要な課題です。ここでは、工場におけるサイバーセキュリティを含む効果的な対策の5つのポイントを解説します。
リスクアセスメントの実施
工場におけるリスクアセスメントは、セキュリティ対策の基盤です。まず、潜在的なリスクを特定し、それぞれのリスクがもたらす影響を評価します。
リスクアセスメントを実施することでどのリスクが優先的に対策を講じるべきかが明確になるため、無駄なコストを削減し、効果的なセキュリティ対策を講じることが可能になります。
リスクアセスメントの際には、まず、工場内の各エリアやプロセスを詳細に分析し脆弱性を洗い出しましょう。例えば、アクセス制御の不備や、機密情報の漏洩リスクなどが挙げられます。リスクをリストアップし影響度と発生頻度を評価することで、優先順位をつけます。
リスクアセスメントを定期的に実施することで、常に最新のリスクに対応したセキュリティ対策を維持することが重要です。
セキュリティポリシーの策定
セキュリティポリシーは、工場全体のセキュリティ対策を統一的に管理するための指針となります。ポリシーを策定することで従業員全員が同じ基準に基づいて行動し、セキュリティの一貫性を保てるようになります。
ポリシーを策定する際には、組織の目標やリスクアセスメントの結果を考慮したうえで具体的な行動指針を定めなければなりません。例えば、アクセス権限の管理方法や、情報漏洩防止策などを含めることが考えられます。
また、ポリシーは定期的に見直し、必要に応じて更新することで常に最新の状況に対応したものにすることが重要です。定期的な更新により工場全体のセキュリティレベルを維持・向上させることが可能になります。

NIST CSF2.0(NIST サイバーセキュリティフレームワーク)とは?概要・メリット・導入方法を解説
本記事では、NIST CSFの概要、バージョン2.0の変更点、構成要素、導入メリットなどを分かりやすく解説します。企業がNIST CSFを活用して効果的なセキュリティ対策を実施するための情報を提供します。
従業員教育の実施
従業員教育は、工場のセキュリティ対策を実効性のあるものにするために欠かせない要素です。従業員がセキュリティの重要性を理解し適切な行動を取ることで、リスクを未然に防げます。
教育の実施方法としては、定期的な研修・セミナーの開催や、最新のセキュリティ情報や対策の共有が効果的です。また、具体的な事例を用いたケーススタディを行うことで、従業員が実際の状況に即した判断を行えるようにすることも重要です。
教育内容は常に最新の情報を反映し継続的にアップデートすることで、従業員のセキュリティ意識を高い水準で維持することが可能になります。
セキュリティシステムの導入
セキュリティシステムの導入は、工場の物理的および情報的なセキュリティを強化するための重要な手段です。適切なシステムを導入することで不正アクセスや情報漏洩を防ぎ、工場全体の安全性を向上させられます。
システム導入のメリットとしては、監視カメラやアクセス制御システムによる不審者の侵入防止、ネットワークセキュリティの強化による情報漏洩防止などが挙げられます。
システムを選定する際には、工場の規模や業務内容に応じた適切なシステムを選ぶことが重要です。例えば、大規模な工場では広範囲をカバーできる監視システムが必要となる場合があります。
また、選定にあたっては、導入後の運用コストやメンテナンスの容易さも考慮しなければなりません。導入後の運用やメンテナンスまで考慮したシステム選定により、長期的に安定したセキュリティ対策を実現することが可能になります。
定期的なセキュリティ監査
定期的なセキュリティ監査は、工場のセキュリティ対策が適切に機能しているかを確認し必要な改善を行うために欠かせません。監査を通じて既存の対策の効果を評価し、新たなリスクが発生していないかをチェックできます。定期的な監査により、常に最新のセキュリティ状況に対応した対策を講じることが可能になります。
監査の実施方法としては、内部監査と外部監査の両方を組み合わせることが効果的です。内部監査では、日常業務に精通したスタッフが現状を詳細に分析し、改善点を洗い出します。
一方、外部監査では第三者の専門家による客観的な視点からの評価を受けることで、見落としがちなリスクを発見できます。定期的な監査を行うことで工場のセキュリティ対策を常に最適な状態に保ち、リスクを最小限に抑えることが可能です。
関連ガイドラインと規格
工場のセキュリティ対策を効果的に実施するためには、関連するガイドラインや規格を理解し、適切に活用することが重要です。ガイドラインや規格は、工場のセキュリティを強化するための基準を提供し、リスクを最小限に抑えるための指針となります。
工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン
国内のガイドラインとしては、経済産業省が提供する「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」があります。このガイドラインは、日本国内の工場におけるセキュリティ対策の基本的な考え方や具体的な実施方法を示しており、特に中小企業にとって有用です。
IEC 62443
IEC 62443とは、産業用オートメーションおよび制御システム(IACS: Industrial Automation and Control Systems)のセキュリティを確保するために策定された国際標準規格です。制御システムの構築・運用に関わる組織や企業が、サイバーセキュリティ上の脅威からシステムを保護し、リスクを最小限に抑えることを目的としています。

重要インフラを守る!IEC 62443でICS/OTセキュリティ対策を強化
IEC 62443は、産業制御システム(ICS)やOT環境におけるセキュリティを確保するための「国際標準規格」です。 本記事では、IEC 62443の概要、構成、準拠のメリット、対応方法に加え、導入事例も交えて解説します。
ISO 27001
国際的に広く認知されているISO 27001は、情報セキュリティ管理の国際規格であり、第三者機関による認証取得も可能です。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の構築と運用に関するフレームワークを提供し、情報漏洩や不正アクセスのリスクの低減につなげられる規格です。
ISO 28000
工場の物理的なセキュリティを強化するためにはISO 28000の認証取得も検討する価値があります。ISO 28000はサプライチェーンセキュリティ管理システムに関する規格で、工場の物流や製品の安全性を確保するための基準を提供します。ISO 28000を導入することで、サプライチェーン全体のリスクを評価し適切な対策を講じることが可能です。
制御システムのセキュリティ
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が発行している「制御システムのセキュリティ」は認証制度ではありませんが、実践的なセキュリティ対策の指針として広く活用されています。
こうしたガイドラインや規格、必要に応じて認証の取得を活用することで、工場のセキュリティ対策を体系的かつ効果的に進められるでしょう。各工場の特性やニーズに応じて適切なガイドラインや規格を選択し、実践することが、セキュリティリスクの低減と生産性の向上につながります。
まとめ
工場におけるセキュリティ対策は、生産性や品質を守るだけでなく企業の信頼性や競争力を維持するためにも欠かせない取り組みです。サイバー攻撃や内部不正、情報漏えい、サプライチェーン攻撃など、製造業が直面するリスクは年々多様化・深刻化しています。
こうしたリスクに備えるためには、リスクアセスメントの実施、セキュリティポリシーの策定、従業員教育の強化、システム導入、定期的な監査といった複数の視点から対策を講じることが重要です。
加えて、ISO 27001やISO 28000といった国際規格の認証取得や、経済産業省・IPAが提供するガイドラインの活用も有効です。自社の規模や体制に合わせて、段階的かつ体系的にセキュリティ対策を進めましょう。
TXOneにまずお気軽にご相談ください。
製造業界のサイバーセキュリティ課題は常に変化しています。TXOneはお客様のサイバーセキュリティに関する課題について最適なOTセキュリティソリューションが提供できるよう、いつでもお手伝いさせていただきます。お問い合わせ内容を確認後、担当者より迅速にご連絡致しますので、お気軽にお問合わせください。
おすすめ記事

Volt Typhoon:忍び寄る脅威とサプライチェーンの盲点
本記事では、古いルーターやパッチ未適用のエッジデバイスを悪用するVolt Typhoonの手口と、見過ごされがちな信頼の裏に潜む危険について解説。運用環境の可視化やSBOM、セキュア・バイ・デザインといった対策の必要性も紹介します。